TOEICで875点を取得しました!
私は、約3か月間の勉強の末、2021年2月のTOEIC公式テストで875点を取得しました。
別に仕事で英語を使うわけでもなく、海外に興味がある訳でもないのですが、いろいろあって取得をしました。
しかし、特に目的も無かったのと、これ以上英語を勉強する意味が見出せず、取得後は一切英語の勉強はしていません。
今回は、私がTOEIC875点を取得するために行った勉強方法と、取得した後に感じる自分の英語力、そしてせっかくハイスコアを取得したのに英語の勉強を辞めてしまったことについて話していきたいと思います。

それじゃ行きましょうか!
勉強方法について
私の経歴
まずは私の経歴について簡単に紹介をします。
学歴と職歴
| 大学 | 理系国立大学(化学系) |
| 大学院 | 同大学(製薬系) |
| 会社 | 大手化学メーカー(工場勤務) |
こんな感じで、特に英語とは縁のない生活をしていました。
英語と使う場面といったら、研究室時代に論文を読むときくらいですが、ビジネス英語とはかけ離れており、しかも訳すのが面倒だったのでほとんど自動翻訳機にぶち込んでいました。

TOEICに出題されるようなビジネス英語とは無関係な生活を送っていたんだね
次にTOEICの受験歴についてです。
TOEIC受験歴
| 時期 | 目的 | スコア |
| 大学1年生 | 入学テストで受けた | 525点(IP) |
| 大学3年生 | 進級のため | 680点(IP) |
| 大学4年生 | 大学院入試で使うため | 720点(公式) |
| 社会人1年目12月 | 用途なし | 780点(公式) |
| 社会人1年目2月 | 用途なし | 875点(公式) |
学生時代は必要に迫れられるタイミングで受験をしてきました。2回目の受験は、卒業要件が650点だったから、3回目の受験は就活にも使えると思ったから頑張りました。
社会人になってからは、特に仕事上での用途はないのですが、今後のことを考えて取り敢えずスコアを取っておきました。
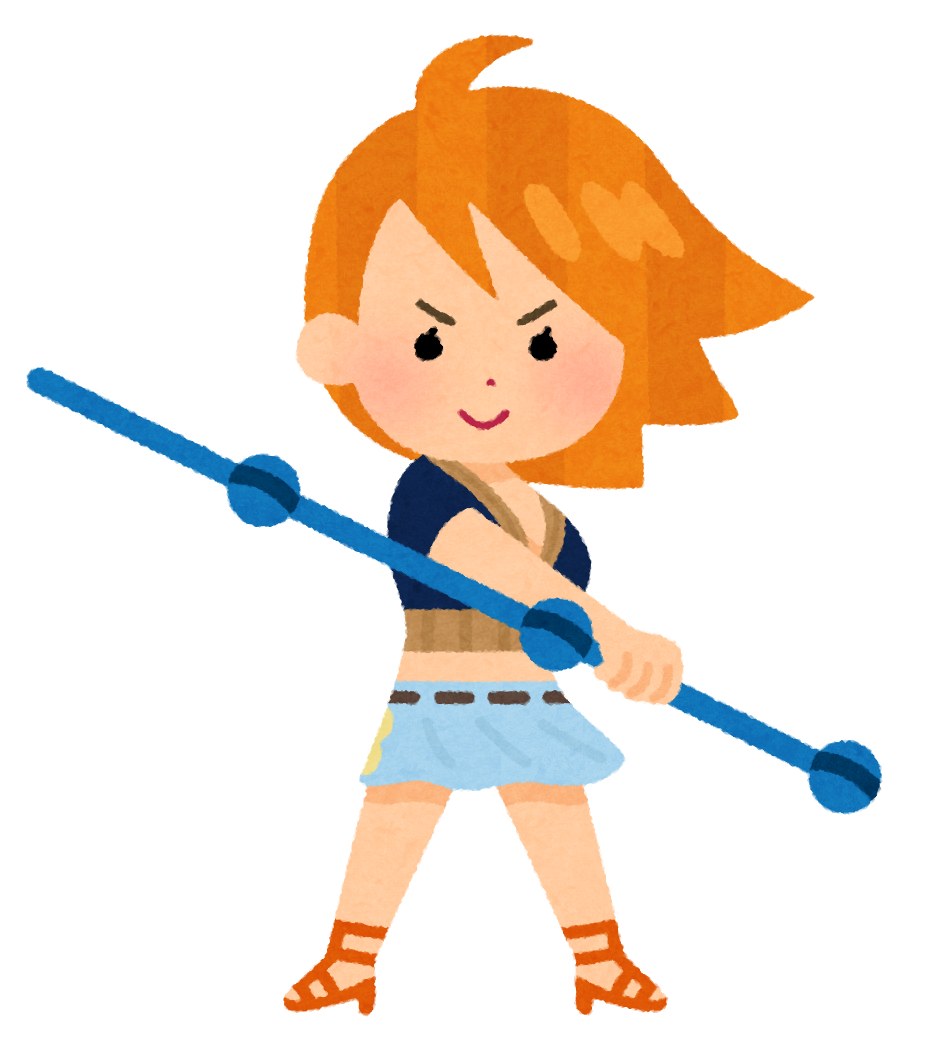
何やかんやでTOEICを受験するたびにスコアは上がっているね...
受験の目的

続いて、社会人になってからTOEICを受験した目的です。
正直なところ、大きな目的は無かったのですが、強いて挙げるならば、今後転職を検討する時に役立つと思ったからです。
英語自体は特に苦手意識はなく、学生時代に取得したスコアに対しても、「自分の英語力はこんなもんじゃないはず...」という謎の過信があったので、暇な社会人1年目のうちに勉強を頑張りました。
TOEICは転職市場でも未だ根強い人気がありますが、その理由は社会人なら誰でも受けたことがあるからだと思います。
故に、その人のスコアから直感的に英語力が予想できるのですが、しばしばハイスコアは過大評価されていると感じます。
それはおそらく、評価する側の英語力が低く、自分のより高いスコアに対しては未知の領域になるからだと思います。

今になって思うのは、当時は目的も無かったのによく勉強できていたな…
私が行ってきたTOEICの勉強方法

TOEICの勉強は純粋な英語の勉強とは違って、特別な対策が必要になります。
もちろん、最終的に英語力を上げることを目的とする人は、手段としてのTOEIC勉強で良いのですが、私は特にそんな目的はなかったので、TOEICでスコアを取得することを目的とした勉強方法を採用しました。
そこで採用したのが、スタディサプリです。
特に宣伝をするつもりはないですが、TOEIC対策に特化しており、スマホ片手に勉強ができるので、短時間で効率的にスコアアップを図りたい社会人にはおススメの教材だと思います。
※ただし、センター試験(共通試験)で7~8割も取れない人は、別途参考書で大学受験の単語・文法の基礎をやり直した方が良いです。
アプリ内にも基礎講座はありますが、適当な作りになっているのでおススメしません。
スタディサプリではPart毎の対策が行えるので、次にPart毎の勉強方法について紹介していきます。
スタディサプリがどんなアプリなのかはどこか別のサイトで調べてください。

自分で3ヵ月で875点とか書いといてアレだけど、~ヵ月で~点アップ!!って言って自分の努力を安売りしてくる人には気を付けてね
Part1(リスニング:写真)

このPartでは写真を見て設問に答えます。行った勉強方法は主にディクテーションです。
このPartでは知らなきゃ解けない頻出単語・熟語(curbやcast a shadowなど)と、お決まりのパターン(受動態、have beenとbeing、消去法で解くなど)がいくつかあるのですが、それは演習を繰り返す内に自然と身に付いていきます。
そのため、ディクテーションで短文を聞き取れるようにしておけば、Part1独特の雰囲気も感じ取れるようになるので、本番も1ミス程度で済むと思います(どうしても毎回1問くらいは難問が出る)。
Part2(リスニング:質疑応答)

このPartでは、短い質問に対する解答を選びます。行った勉強方法はPart1と同じくディクテーションのみです。
ここのPartの対策で良く最初の単語を聞き逃すなという話がされていますが、実際は全ての単語を聞き取れないといけません。
Whyで始まってBecauseで答える超簡単問題なんて1問くらいしか出ません。
大事なのは全体を聞いて何を聞いているのかを理解することです。
そのため、ディクテーションでの勉強が効いてきます。
英語はリンキングといって単語同士が繋がることで、シームレスに文章が話されます。
そのリンキングを把握するのにディクテーションが最適で、これにより重要な単語も聞き逃さなくなり、正答率が上がります。
また、このPartも先ほどと同様にお決まりのパターンがあるので、それも演習を繰り返す内に分かると思います(時制の一致、定型文、ハズしなど)。
Part3(リスニング:2~3人での会話)

このPartは30秒程度の会話に関する設問に答えます。
行った勉強方法はシャドーイングです。
文章が少し長くディクテーションがきついのでシャドーイングにしました。
アプリの音読機能を使って毎日やっていました。
シャドーイングのやり方は調べればいくらでも出ると思いますが、一つだけ注意しなければいけないのが、ちゃんと意味を理解した文章で行わないと意味がないことです。
一度解いた問題を全て和訳して構文を理解した後に、初めてシャドーイングをする意味が出てきます。
また、解答するとき、先に設問を読む人とまとめて解く人とで分かれますが、私は設問の先読み派でした。
このPartでは、聞き取れても解答するときには忘れちゃうということが良くあったので、ポイントを押さえてリスニングするのが自分には合っていると感じました(特に職業、場所、時間などは確実に確認)。
そのため、設問を一瞬で理解できるようにするための勉強もしました(設問の構文はほぼ同じ)。
このPartも例に漏れずパターンはあります(会話の内容、設問で聞くこと、TOEICの世界観など)。
Part4(リスニング:一人で喋る)

このPartはPart3と違って、一人が30秒程度しゃべり続け、その内容について答えます。
勉強方法はPart3と全く同じで、問題の解き方や対策もほぼ同じなので割愛します。Part4にもパターンはあります。
Part5(リーディング:文法:語彙)
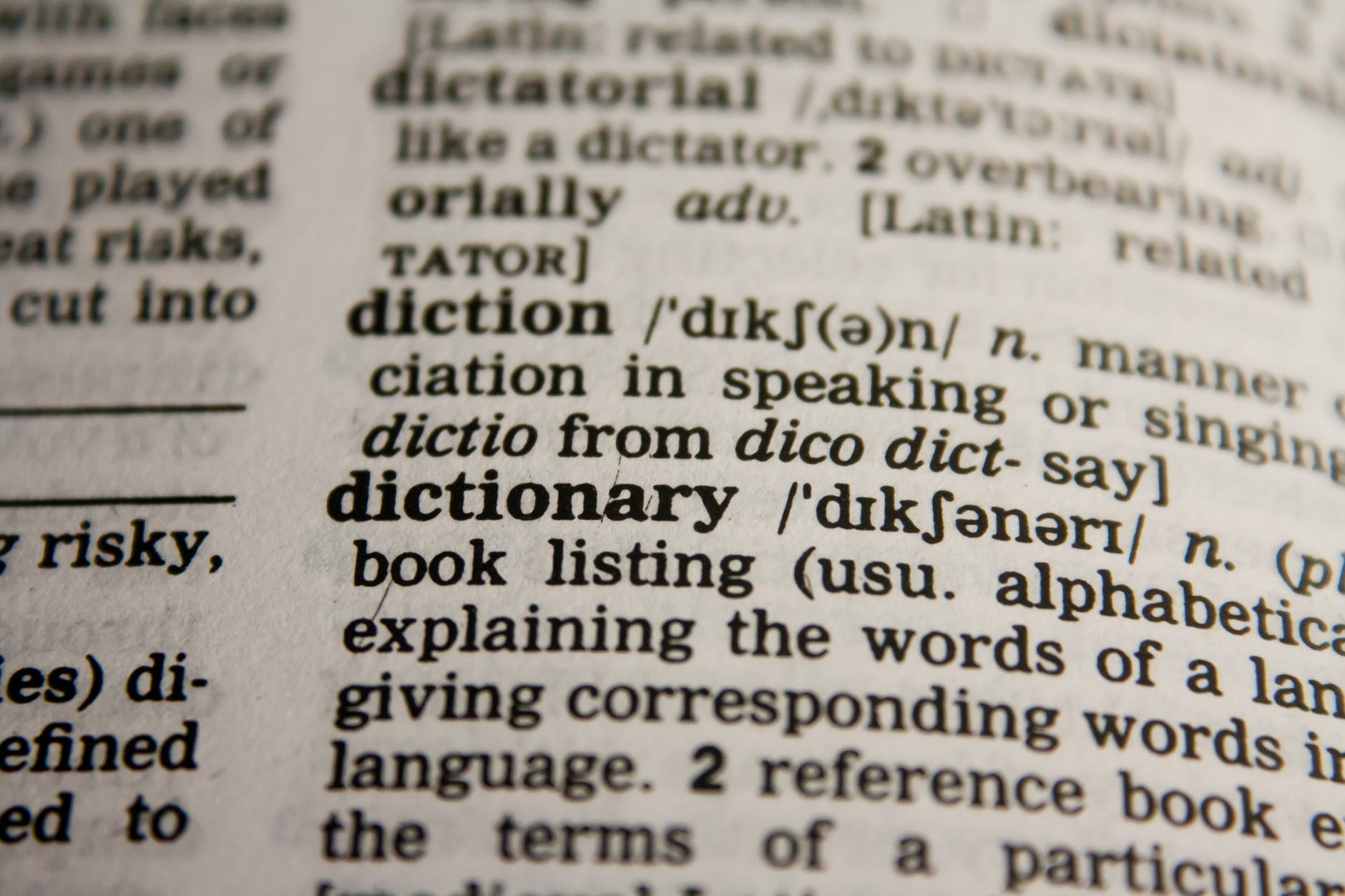
このPartは文法・語彙の穴埋め問題です。
行った勉強はスタディサプリのパーフェクト文法講座と模試のみで、他は特にやっていません(語彙に関しては、金のフレーズを別途購入して行いました)。
多くの人が文法を苦手としていますが、私はむしろ文法は得意な方で、大学受験の貯金で何とか初めから出来たのでそれほど対策はしませんでした(受験期に使用していた単語帳はDuoとターゲット1900で、文法書はネクストステージ)。
文法に関して言うと、文章の意味よりも構造で考えることをおススメします。
文法問題は文章のレベルが高いので、正面から行ってもなかなか解けません。
なので、構文から空欄に入る品詞を絞ったり、時制から選択肢を絞ったりする方法がベターだと思います。
不安な人は大学受験で使うような参考書を購入することをおススメします。
Part6(リーディング:文章空欄補充)

このPartは1分程度で読める文章に設置された空欄を補充する設問です。
行った対策はアプリの問題演習→精読・音読くらいで、特別な対策はしていません。
ここも結局は文法・語彙の延長線みたいなものなので、Part5の対策が出来ていれば特別な対策は必要ないと思います。
あとは、問題の解き方ですが、頭から文章を読んでいって空欄が来たら該当する設問を見るという方法で良いと思います。
特に選択肢を先読みする必要もないと思います。
文脈が分からないと解きにくいようになっているので、素直に頭から読むのをおススメします。
Part7(リーディング:長文読解)

このPartは様々な長さの長文読解です。前半は短めの文章やメッセージアプリの問題、後半は長文や広告に関する問題が良く出題されます。
行った対策は問題演習→精読・音読です。
内容を構文的にも意味的にも理解した文章を読むトレーニングは、Part3、4の対策にも繋がってくるので、結局Part7の対策さえすればTOEICは十分なのではと思うほどです。
一番良いのは、アプリの音読機能でPart7の文章をリスニング問題として聞いて、頭で意味を翻訳する方法です。
内容が一番難しいPart7でリスニングが出来れば、Part3、4は対策なしで解けるようになります。
あとは問題の解き方ですが、短い文章の場合は最初に設問を読んで、何を問われているのかを意識しながら本文を読むことをおススメします。
一方で、長文の場合は、設問1だけを見てから本文を読み、それに該当する箇所にたどり着いたら問題を解き、次の設問2を見て再び本文を読む、という解き方をおススメします。
TOEICの設問は、基本的に文章の流れと同じ流れで出題されているので、1問ずつ解いていくのが良いと思います。
あとは時間配分に気を付けてください。
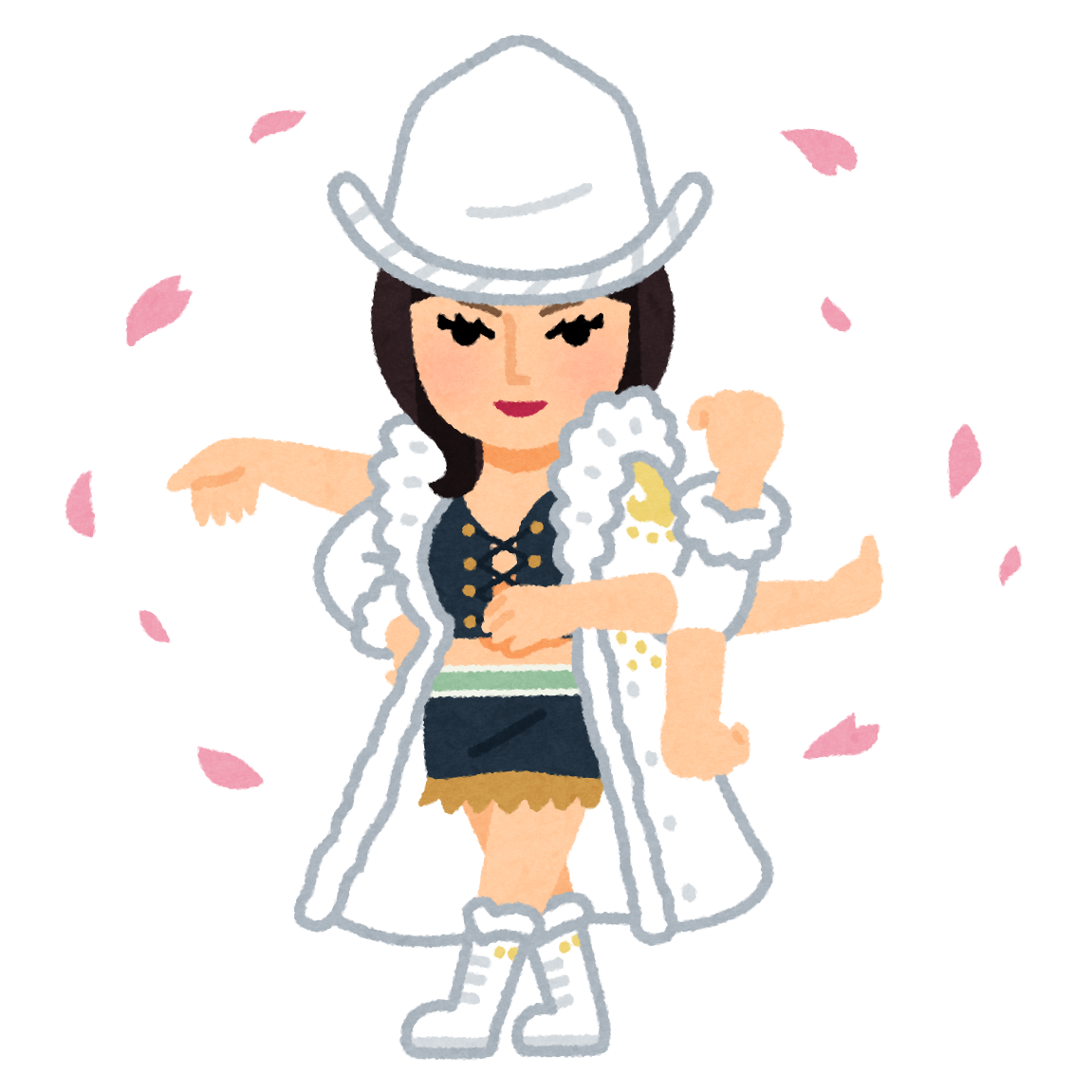
それぞれのPart毎に特色はあるけれど、結局は色々と本質的に繋がっているところがあるのね
スタディサプリの模擬試験もスコア記録(補足)
最後に、私はスタディサプリを始めてから取り組んだ模試(スタディサプリの実践模試テキストを使用)の試験結果の記録を紹介しておきます。
模試は全部で6回解きました。
点数は偏差値性なので、範囲での記載となります。
| Listening | Reading | Total | |
| 1回目 | 405~450 | 350~410 | 755~860 |
| 2回目 | 420~465 | 430~475 | 850~940 |
| 3回目 | 405~450 | 350~410 | 755~860 |
| 4回目 | 450~490 | 410~455 | 860~945 |
| 5回目 | 410~460 | 415~460 | 825~920 |
| 6回目 | 410~460 | 370~420 | 780~880 |
試験の難易度によって点数は100点くらい変わると言われているので、一概には言えませんが、解いた実感としては、後半に行くほど時間的な余裕が生まれ、解答の自信も上がっていった気がします。
TOEICには900点の壁がありますが、800点台から900点台に上げるのはなかなか難しいのだなと感じました。
TOEICは試験慣れをするだけでもスコアは大きく変わってくるので、公式問題集でも良いので、模試を活用して試験慣れと時間配分の感覚を掴んでおきましょう。

TOEICはその時の標準偏差によって素点の結果が大きく変わってくるよね
875点取得後の感想
TOEIC875点を取得して感じる自分の英語力

上記のような勉強方法を行うことで、3か月くらいで875点を取得することができました。
この点数を取る前は、800点を超えている人はみんな英語ペラペラだと思っていましたが、実感としては自分の英語力は、大学入学時に525点を取得した時とあまり変わった気はしないです(因みに875点というと、受験者の上位数パーセントに属するので、全国的に見ればかなり英語ができる方に属します)。
確かにリスニング力は上がりましたが、それ以外は何も変わりません。
TOEICはリスニングとリーディングの試験で、他の勉強はしていないので当然ではありますが。
ただ、スピーキングやライティングに関しても、少なくとも勉強すれば割とすぐ出来るようになるな、と言った謎の自信は身に付きました。
このスコアを取得して思ったことは、ようやく英語のスタートラインに立ったのだなという感じです。

英語の壁は思ったよりも高いね
英語の勉強を辞めた理由について

最後に、ここまでTOEICを頑張ってきたのに、英語の勉強を辞めてしまった理由について話していきます。
なお、以下の内容については、英語をメインで使う方(教師、翻訳家、通訳士など)には一切関係ない内容になります。
英語はあくまで手段
これが一番大きな理由になります。結局、どこまで行っても英語は言語なので、手段にしかなりません。
そう考えた時に、英語を身に付けた後に特にやりたいことや、英語を活かせる状況にいない自分にとっては、今後の保険以外に何の役にも立たないという現実が強すぎました。
TOEICのスコアは保険としては大きな武器になっていますが、それ以上の学習は保険という観点では過剰になってしまうように感じました。
自動翻訳の性能向上
これからの時代、言語の自動翻訳のレベルは加速度的に成長をしていきます。
そうなった時に、同時翻訳をしたり重要な商談を行ったりしない限り、高いレベルの英語を扱えることの重要性は落ちてくると思います。
もちろん、情報収集や簡単な英会話ができる程度のレベルは必要だと思いますが、それ以上の英語力を身に付けることは、費用対効果が低いと判断してしまします。
英語は+αとなって初めて意味を持つ
上記の話と被りますが、英語は言語なので、自分の持っているものを他者に伝えるときに使うツールです。
そのため、まずは個人のスキル(=伝えたいもの)を持っていないと意味がありません。
自分はまだ社会人駆け出しのペーペーで、英語のような表面上のツールを身に付けるよりも、もっと本質的なものを身に付ける必要があると感じてしまいました。
そのため、英語は休止して、自分の専門分野の勉強や、ビジネススキルの勉強に力を注ぐようにしました。

英語はあくまで手段。その認識だけは間違っちゃダメ
あとがき
色々と書いてきましたが、TOEICの勉強をして875点を取得するために割いた時間や労力に対しては特に後悔はしていません。
今後、グローバル化が加速していくのは明らかですし、日本人は英語が全くできないので、スコアを持っているだけで一目置かれる存在となれます。
今後仕事をする上で、英語が必要になるかどうかは分かりませんが、とりあえず必要になったらすぐに身に付けられるレベルには達したので、これからは余裕な心持で本質スキルの習得に時間を割いていきたいです。

読んでくれて、ありがとうございました!