エネルギー管理士(熱)に一発合格しました!
社会人2年目の夏、令和3年度開催のエネルギー管理士(熱)に一発で合格をしました。
試験勉強を開始したのは同年の4月からで、試験日が8月8日だったので約4か月間勉強したことになります。
エネルギー管理士の合格に必要な勉強期間は、それぞれの過去の経歴によって当然変わってきますが、勉強した間隔として、4か月と言うのは平均よりやや少ない時間だと思います。
今回は、私がこの4か月間に勉強した手順や内容について紹介していきたいと思います。参考になれば幸いです。
ちなみに点数の開示はありませんでしたが、自己採点では各科目8割くらい取れてました。

同じ理系出身でも、専攻によって必要な勉強時間は大きく変わってくるね!
自分の経歴
まずは私の簡単な経歴を紹介します。
| 大学 | 理系国立大学(専攻は生命科学) |
| 大学院 | 同大学(専攻は有機化学) |
| 会社 | 大手化学メーカー(工場勤務で2021年現在2年目) |
大学時代は化学や生物に近い学問を専攻しており、物理に関しては大学受験以降、ほとんどやっていませんでした。
(とはいっても、エネルギー管理士に出る熱力学の第一法則、第二法則に関しては基本的には高校レベルなので、大学受験の貯金で最初からある程度理解できた気がします。熱サイクルを覚えるのは時間が掛かりましたが。)
また、大学院では医薬品の研究に従事しており、有機化学が専攻でした。
日夜フラスコを振ってNMRで分析をする毎日でした。
そんな経歴ですが、就活に失敗したことから、何の因果か工場で働くことになり、このエネルギー管理士を受験することに至りました。
別に会社から受けるように言われた訳ではないのですが、工場を広く浅く理解するのに一番適していると感じたから受けました。
以上を簡単にまとめると、
まとめ
- 学生時代は理系だけど、専攻は化学
- 熱力学は高校レベルの理解だけど、それでも割と対応できた
- 流体力学と伝熱工学については完全に素人
では次に、そんな私が試験のために勉強してきた内容について紹介をしていきます。
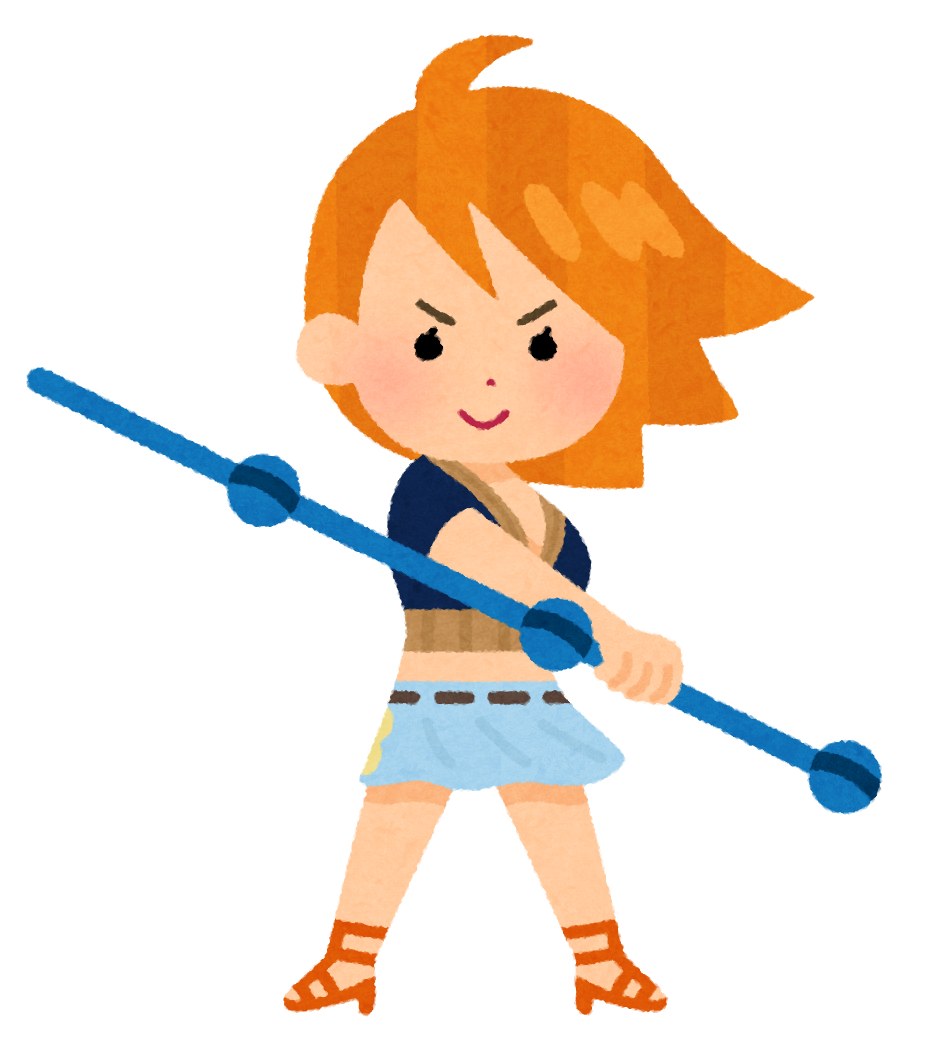
大学受験のレベルでも十分対応できるんだね
エネルギー管理士の勉強方法
続いて、私が行ってきたエネルギー管理士の勉強方法について紹介をしていきたいと思います。
現状把握
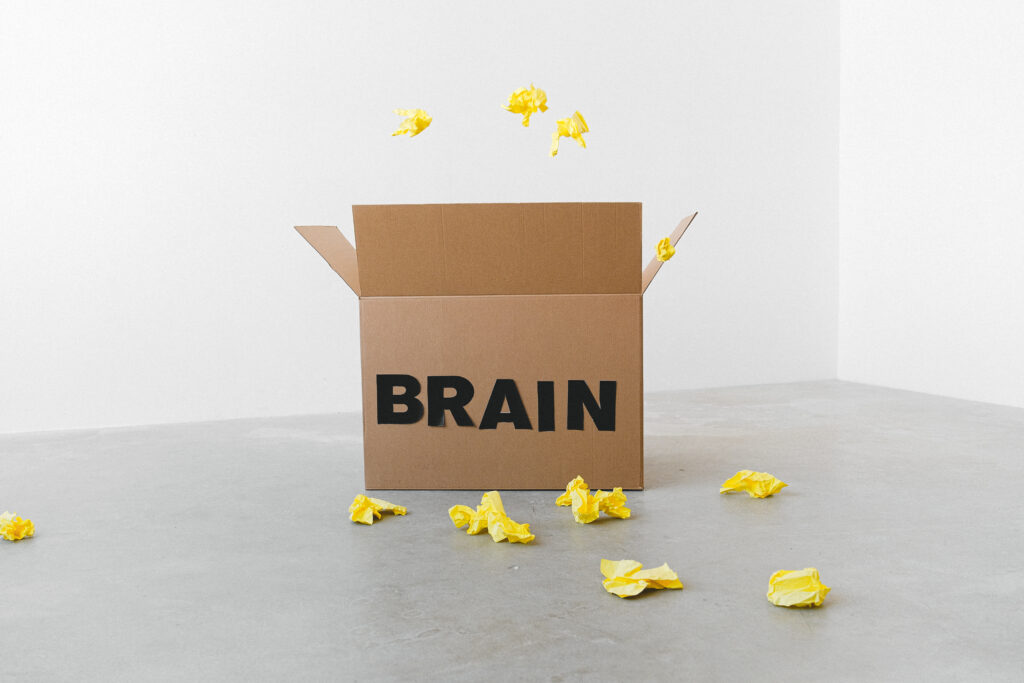
まずは、エネルギー管理士の試験の仕組みについて理解をするところから始めました。
科目合格制度、合格最低点、各科目の試験範囲、試験の出題方法、試験日など、敵の情報についてしっかりと調べ、試験の雰囲気を掴みました。
次に過去問を読んでみて、どの程度理解できるかを確認しました。
おそらく理系の人ならば、科目Ⅱの熱力学と科目Ⅲの燃焼計算問題は何となく理解できると思います。
一方で、法律や熱利用設備、流体、伝熱工学は意味不明でした。いずれにしても、自分が初期スペックでどのくらいのレベルなのかを把握しておくことで、必要な勉強時間を見積ました。
勉強の順番
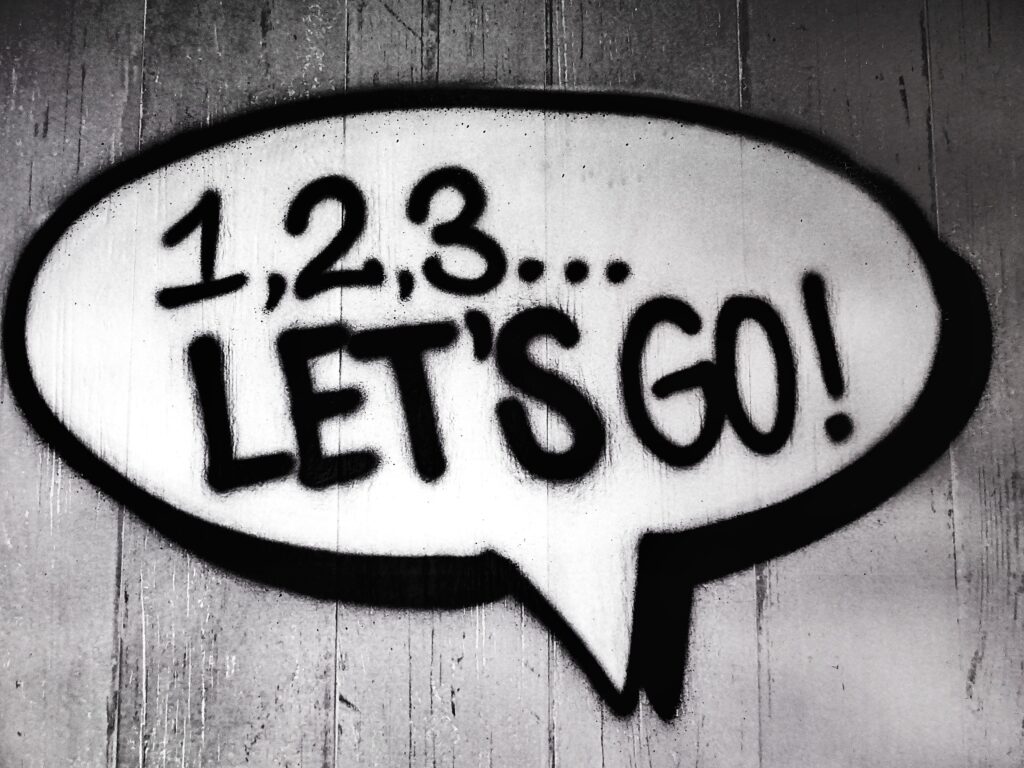
試験の内容が把握できたら、次は実際に勉強のスケジュールを立てました。
エネルギー管理士では全部で4科目の受験が必要になりますが、個人的と言うか世間一般の感覚として、各科目の難易度順は以下のようになると思います。
科目Ⅱ(熱と流体) > 科目Ⅳ(熱利用設備) > 科目Ⅲ(燃料と燃焼) > 科目Ⅰ(法規)
そのため、勉強の順番も難易度に沿って行いました。
各科目の勉強
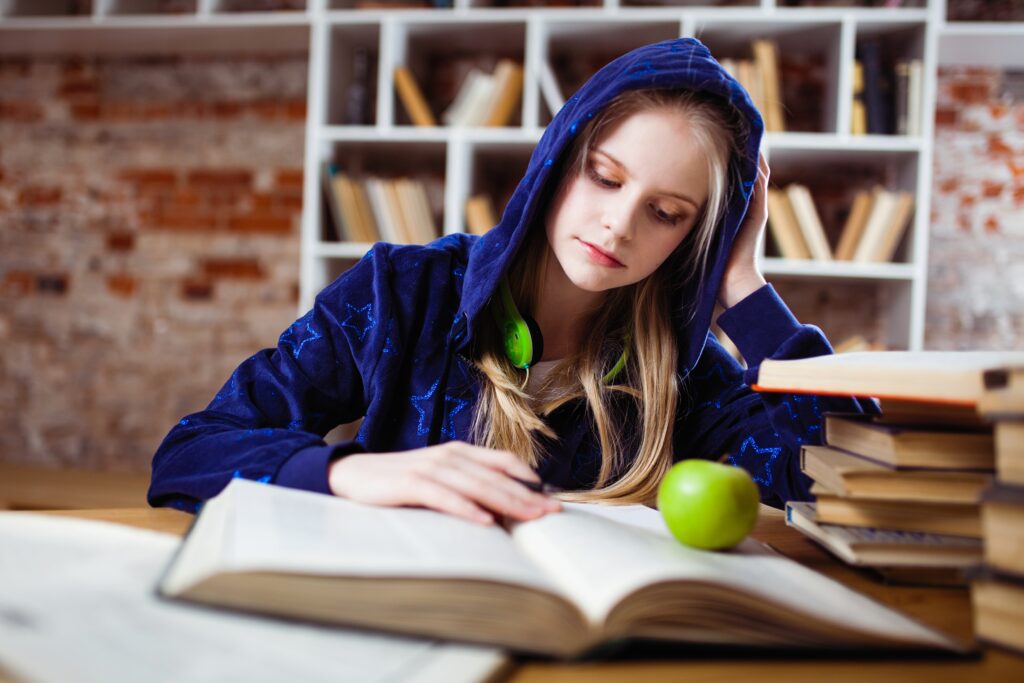
続いて、各科目の勉強内容について紹介していきます。
ですが、その前に覚えておいて欲しいことは、エネルギー管理士は6割取れれば合格になるということです。
そのため、難しくて理解できないところは構わず飛ばしていました。
公式の参考書には、試験に出る全ての範囲が記載されていますが、まずは基本的なところだけ理解するようにしました。
その後、過去問を一通り解いてみて、問題で出題されたけど飛ばしていた内容があったら、追加で再度勉強をしていました。
点数が10割で合格も、6割で合格も同じ合格なので、基本的なところを完全に理解して効率よく合格できるように心掛けました。
難解なところや応用の範囲はどうせ本番に出ても誰も解けないので、とりあえず飛ばしていました。
それで過去問にも出てなかった完全に捨てて良いと思います。
それでは内容に入って行きます。
科目毎の勉強方法
1.科目Ⅱ(熱の流体の流れの基礎)
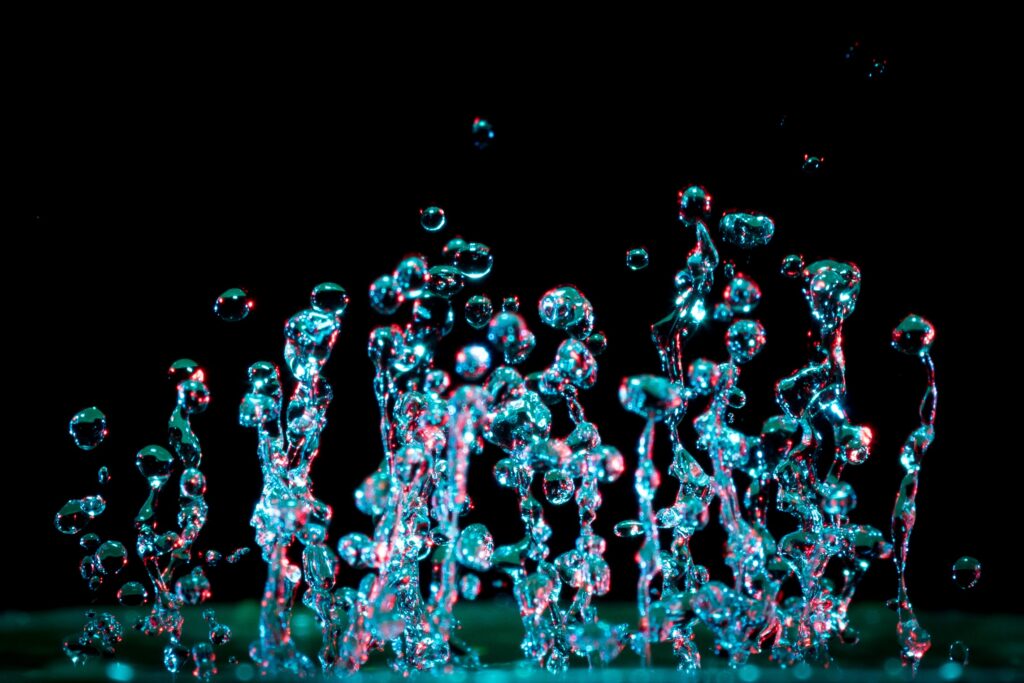
この分野は計算問題がメインです。
そのため、しっかりと原理・原則を理解するようにしました。
科目Ⅱは全部で4つの大問がありますが、そのうちの2つが熱力学なので、特に重点的に勉強しました。
ちなみにこの科目で使用した参考書はこちらです。

熱力学の勉強
熱力学の第一法則は、大学受験の貯金で特に問題ありませんでした。
エネルギー管理士ではエンタルピーに関する問題がメインなので、ここはしっかりと理解するようにしました。
また、熱サイクルも毎年必ず出題されており、特に蒸気サイクルは超頻出なので、再生サイクルと再熱サイクルについては暗記するくらい過去問に取り組みました。
あとはディーゼルサイクルとオットーサイクルの違いなども良く出てきますが、この辺りは科目Ⅳの熱設備の範囲とも被っていたので、後々に回しました。
基本的には、公式の参考書を読んで理解して、過去問で確認って感じです。
流体力学
流体力学は初見の分野で意味が分かりませんでしたが、こちらのYouTubeを見ると良く理解できました。
これを一通り見ればだいたい理解できるので、そのあとに上記の参考書を何回か読んで、後は過去問演習で充分対応できます。
ただ参考書に出てくる基本的な公式(ベルヌーイの定理、ハーゲンポアズイユなど)の算出は出来るようにしました。
流体は自分で公式を算出できるようになれば、おそらくどんな計算問題もだいたい対応できると思います。
意外と点数の稼ぎどころだと感じました。
伝熱工学
伝熱工学は毎年同じような問題しか出ないので、参考書を一通り読んで、あとは過去問で充分だと思います。
参考書には複雑な式が出てきますが、応用は飛ばして基礎だけで良いと思います。
過去問を見てみても、近年は素直な問題しか出てきてないです。
ただ、無次元数については覚えておかないと全滅する分野なので、意味が分からなくても公式を暗記するようにした方が良いと思います。

この科目は、原理・原則を理解することとパターンになれることが大切なんだね
2.科目Ⅳ(熱利用設備及びその管理)

この科目はほぼ暗記でした。一つ一つの内容は難しくないですが、量が膨大なので早めに対策をするようにしていました。
やったことは参考書と過去問にひたすら取り組んで、用語を覚えることとパターンに慣れることだけです。
使用した参考書はこちらです。
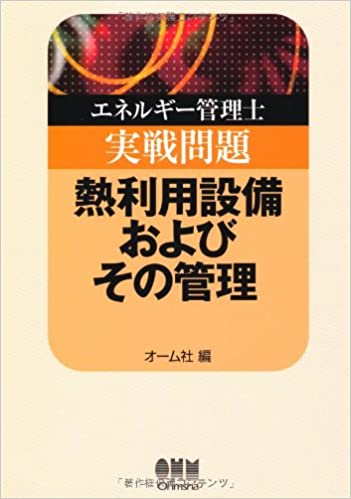
この参考書の問題演習を2周くらいしたら後は過去問で対応しました。
計測
意外とマニアックな問題が出るので、過去問で出てきたものは必ず押さえておきましょう。なんならここだけ多めに過去問を解いても良いと思います。
特に温度計の問題は良く出るので抑えておきましょう。
制御
制御の分野は学問としてはとても難しいですが、過去問を見るとほぼ同じ内容しか出ていないことが分かるので、浅く学習してコスパ良く行きましょう。
完全なパターン問題か、難しい問題の二極化なので、パターン問題以外が出たらもう捨てちゃいましょう。
ボイラ、蒸気輸送・貯蔵
この分野に関しては、ボイラについてどの程度知っているかがカギになります。
参考書の図だけ見ても良く分からない時は、ネットで色々と検索をして、まずはボイラの構造についてしっかりしたイメージを持ちましょう。
その後に参考書を読めば、かなり理解しやすくなるので、効率的に進められます。
内燃機関、ガスタービン
個人的に、この分野は結構難しく感じました。
この分野に関しても、ボイラと同じでタービンについてどの程度知っているかがカギになります。
同様にネットなどで構造を調べて、イメージを持てるようしておきましょう。
また、この分野は科目Ⅱの熱サイクルとも関連が深いので、ここでしっかりと理解をしておくと、科目Ⅱにも良い効果が出るのでしっかり押さえておきましょう。
熱交換器・熱回収装置
この分野は比較的簡単だと思います。
計算問題がメインになりますが、それも簡単な熱収支の問題しか出ないので、基本を押さえておけば対応できます。
熱交換器の種類についても、限られた少数しか出題されないので、それらの特徴は抑えておきましょう。
冷凍・空気調和設備
正直、この分野が一番難しいと思います。
もともと冷凍設備関係の資格を持っている人には簡単だと思いますが、正直私は最後まで良く分からなくて捨ててました。
最低限、蒸気圧縮式冷凍機と吸収式冷凍機の違い、空気線図の理解が出来ていれば、半分くらいは取れます。
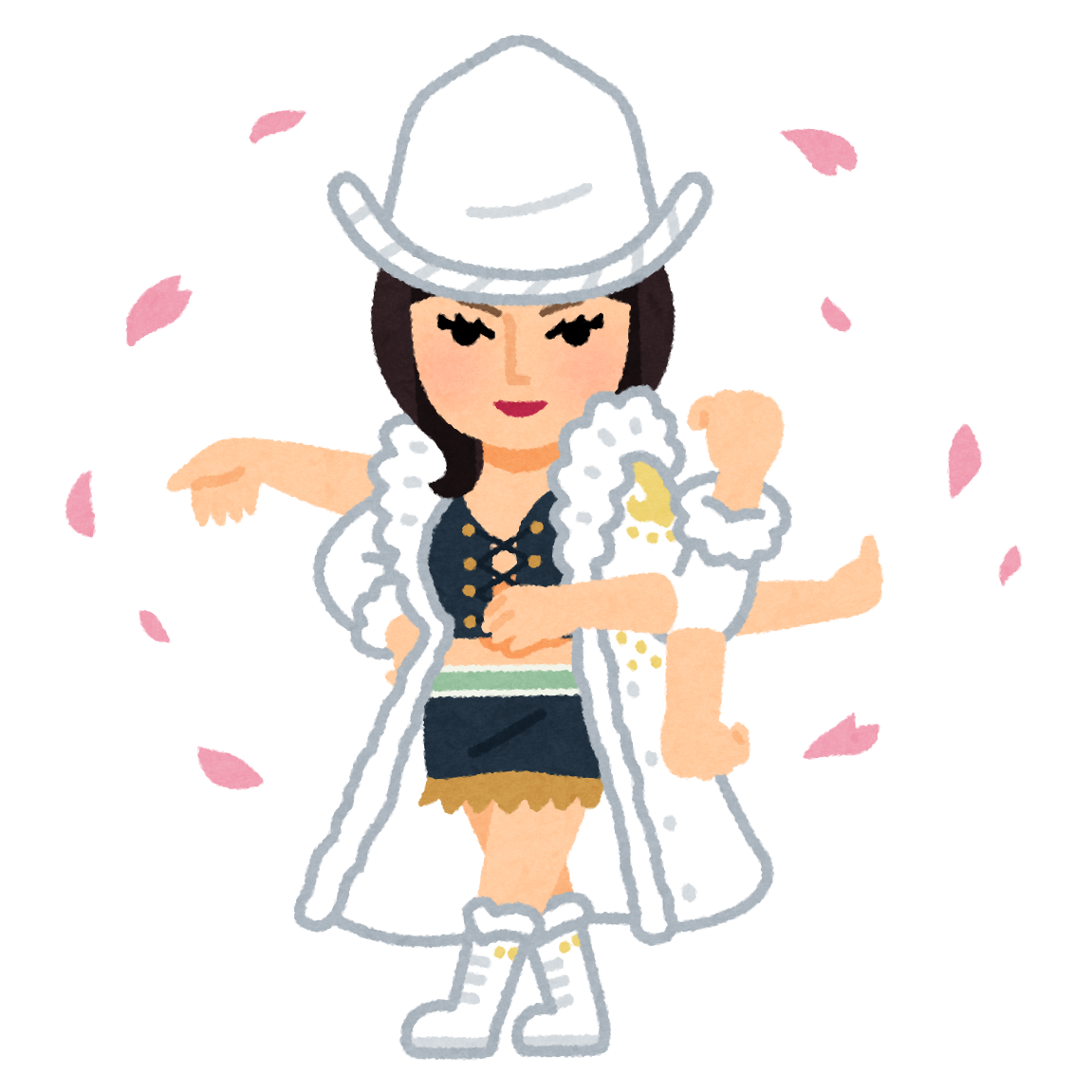
この科目は、実際に工場で設備に触れてきた人にはイメージしやすいけど、知らない人にはただの暗記科目ってわけにはいかないわね
3.科目Ⅲ(燃料と燃焼)

この科目は大きく2つに分かれており、半分が燃料関係の暗記問題、残り半分が燃焼に関する計算問題です。
この科目の特徴としては、燃焼の計算問題が毎年ほぼ同じ問題なので、ここでほぼ満点を取れれば前半の暗記は勉強をしなくても良いという点です。
使用した参考書はこちらです。

燃料及び燃焼管理
ここはほぼ暗記ですが、軽く押さえておくだけで半分くらいは取れる内容になっています。
各種燃料の特徴や燃焼バーナーの特徴、燃焼方法の特徴、排気ガスの問題などについてさらっと覚えておけば半分は取れるので大丈夫です。
残りは後半の計算問題でカバーできるので、この暗記にたくさん時間を費やす意味はないです。
燃焼計算
この分野は毎年同じ形式の計算問題しか出ません。
内容はほとんど大学受験の範囲なので、受験で化学をやっていた人はほぼノー勉でも対応できると思います。
ただ、後半の方はやや難しくなるので、過去問を見て解き方を覚えておきましょう。
科目Ⅲは前半で4~5割、後半で7~8割取るようなイメージで勉強を進めると良いと思います。

この科目はそんなに力を入れなくても合格できるから、力を入れすぎないであくまで6~7割を狙うくらいで良いかもね
4.科目Ⅰ(エネルギー総合管理および法規)

最後は、法規です。
この科目はよく2週間前からでも間に合うと言われていますが、実際にそうだと思います。
過去問を見てみると、半分近くが毎年同じ問題で、複雑な計算もないので直前の詰め込みで間に合うとは思います。
しかし、そうやって舐められているからか、意外と法規だけを落とす人は多いです。
簡単な内容だしほぼ暗記だけなので、1か月前から過去問を解き始めて長期記憶に落とし込み、確実に合格しましょう。
試験当日は法規からスタートなので、ここで楽々合格してリズムを作る上でも実は非常に大切な科目です。
注意点
エネルギー管理士の試験範囲はかなり広いので、勉強しているうちに昔やっていたことを忘れてしまうことが多々あります。
なので、暗記科目に関してはまとめてやると言うより、こまめに復習をして長期記憶に落とし込むようにしましょう。
試験日の心得
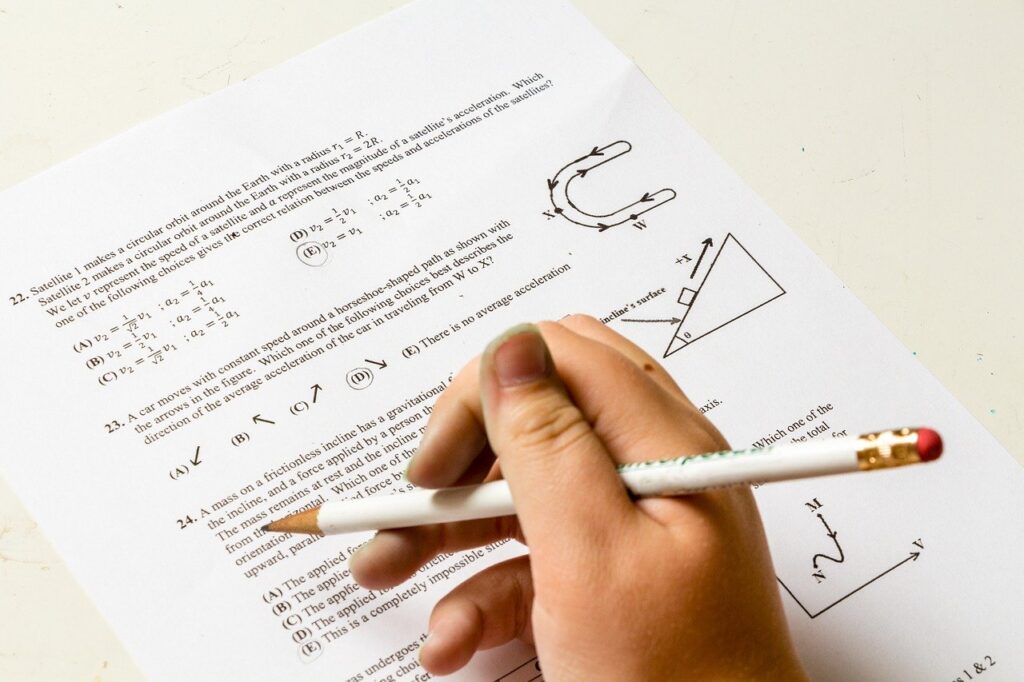
長かった試験対策が終わり、いよいよ受験日です。
当日に実力を発揮できるように色々と準備をしておきましょう。
4科目全て受ける人は1日がかりハードスケジュールになります。
前日はしっかり寝ましょう。
それから電卓と時計の準備は忘れずに。
電卓に関してはルートの計算ができることを確認しておきましょう。
試験当日の心得
①絶対にマークミス、計算ミスをしないこと
②時間いっぱいまで粘ること
まず、①に関してですが、良く自己採点では受かっていたのに実際には落ちていたという話をよく聞きます。
マークの見直しは何回も行いましょう。
それから計算ミスですが、エネルギー管理士では小数点第2位まで問いてきます。
途中計算の四捨五入の桁数を間違っただけで、考え方が合っていても不正解になることがあります。
端数の扱いについては事前に確認しておきましょう。
それから、当日の計算は最低でも2回は電卓で確認し、また、電卓の数値の読み取り、解答用紙への記載にも細心の注意を払いましょう。
良く、計算ミスで落ちたということをまるで運がなかったかのような言いぶりで言う人がいますが、それも実力のうちなので、自己責任です。
簡単な問題を確実に取ることが合格への一番の近道です。
次に②ですが、時間が余っても途中退出は止めましょう。
問題を解き終わった時点で、自信のある問題で勘違いミスをしていないか再度確認をし、計算についてもメモしておいた式や代入した数値、電卓での計算に入力ミスはなかったか確認しましょう。
退出可能になったらすぐに出る人がいますが、別に早く終わったところでボーナスポイントは付かないのでメリットはないです。
次の科目の勉強をするより、目の前の試験を確実に合格させる方に力を注ぐ方が明らかに得なので、イキらないで泥臭く最後まで確実に点数を固めていきましょう。
試験で疲れたなら、退出しないで自分の机で寝ましょう。

満点を狙うんじゃなくて、標準問題を確実に抑えてあくまで合格ラインを取りに行くことが大切だね
まとめ

以上、長々と書いてきましたが、エネルギー管理は時間をかけてやれば受かる試験です。
問題自体はそれほど難しくなく、過去問と似たような問題がでるので、勉強時間との勝負になると思います。
社会人の方は忙しくてなかなか時間を捻出できないと思うので、ポイントだけ抑えて効率的に合格できるようにしましょう。

以上、ありがとうございました!